この記事では確定申告の種類や流れ、そして確定申告にあたって注意したいことについて説明していきます。
自営業の人はもちろん、退職した人、副業などで収入を得ている会社員の人も必要になるものなので、しっかりと目を通しておきましょう。
2019年度(2020年)の確定申告期間
- 2019年度(2020年)の確定申告期間は、2019年2月17日(月)〜3月16日(月)です。
確定申告とは
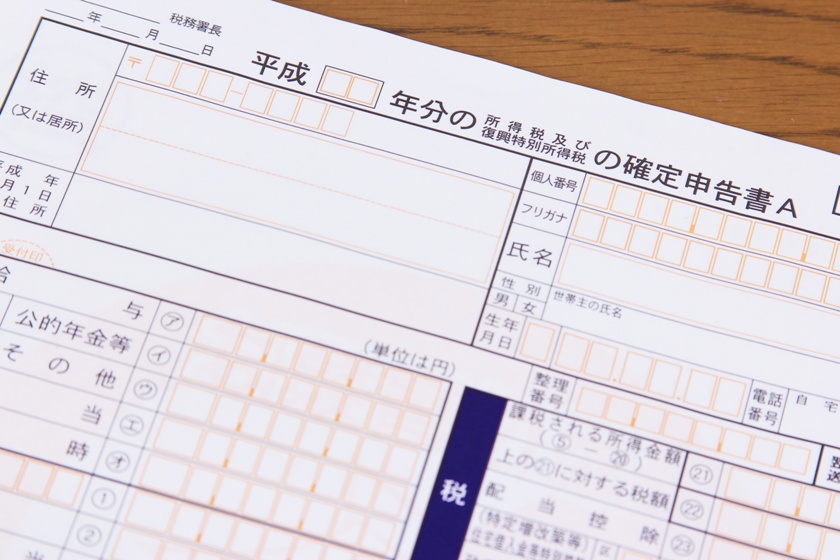
確定申告は私たち国民の義務である「納税」のための手続き
私たちは毎年「所得税」や「復興所得税」を納める必要がありますが、これらの税額は個人の所得額などによって大きく変わってくるので、その年の売り上げや経費、そして控除のお金などを計算して申告しなければなりません。
会社員の場合は、勤め先の会社が自分にかわって納税金額を計算し、給与から天引きして納めてくれるのが一般的です。
確定申告が必要な人
確定申告が必要になる人は、主に自営業の人です。
年間の所得が基礎控除の38万円を超えると必ず必要になります。
ただし、このような自営業の人だけではなく、一部以下のような退職した人や会社員の人の場合も、確定申告が必要になります。
退職した人で確定申告が必要なのは・・・
- 年内中に再就職していない人
会社員で確定申告が必要なのは・・・
- 給与所得が2,000万円以上ある人
- 年末調整を受けている会社以外にも、副業などで仕事を受けており、そこでの収入が20万円以上ある人
会社員の人は、税金を多く払いすぎていた場合に、その分が戻ってくるための手続きとして「年末調整」というものを会社で行なっていますが、上のようなケースに当てはまる場合は、年末調整とは別に確定申告をする必要があります。
退職した人は、年内中に再就職をしていない場合に、確定申告が必要になります。年内中に再就職をしていれば、再就職先の会社で年末調整をできますので、確定申告は必要ありません。
他にも、公的年金等の年間の収入金額が400万円以上ある人や、株取引や不動産による収入がある人なども、確定申告が必要になります。
青色申告と白色申告
確定申告には「青色申告」と「白色申告」という2種類の方法があります。それぞれの特徴を簡単にまとめると、下記のように整理できます。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人に限られている。
青色申告
青色申告で確定申告をすると、10万円の控除か65万円の控除を受けることができる
そのかわり、白色申告の時とは違って事前に「※ 青色申告承認申請書」という書類を提出したり、65万円の控除を受けるためには、より細かい帳簿付けが必要になる「複式簿記」という方法で申告する必要があります。
こういった控除が受けられる他にも、青色申告で確定申告すると、赤字を3年間繰越す事ができるので家族への給与を経費として計上できるといったメリットもあります。
※ 青色申告承認申請書は、青色申告で確定申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に事業をスタートした場合は、スタートした日から2ヶ月以内)に提出する必要があります。
※3月15日が日曜日だった場合、翌日16日月曜日までになります。
例えば2019年分の確定申告を青色申告で申請したい場合は、2020年3月16日(月)までに税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。
必要な書類は税務署か国税庁のサイトからダウンロードできます。
参考サイト:国税庁「所得税(確定申告書等作成コーナー)」
白色申告
青色申告のように10万円や65万円の控除がつかない
白色申告の場合、事前に申請書を提出したり細かい帳簿付けが必要な「複式簿記」で申請する必要がないので、青色申告の時よりも簡単に手続きができます。
青色申告で10万円の控除が受けられる場合と同じ「単式簿記」という方法で手続きをします。
確定申告する際の流れ

確定申告の流れは以下の通りです。
step
1申告に必要な書類などを準備する
まずは確定申告に必要な書類などを準備しましょう。
- ① 確定申告書A( 収入・経費・控除の金額などを記入する書類。会社員や年金所得者用 )
- ② 確定申告書B( フリーランスや分離課税対象の所得(※1)がある人用 )
- ③ 青色申告決算書( 一般用・農業所得用・不動産所得用の3種類あるが、通常は一般用でOK )
- ④ 必要経費の領収書など( 支払った医療費の合計がわかるレシートなども )
- ⑤ 源泉徴収票
- ⑥ その年の売り上げや収入などがまとまったデータ
- ⑦ 印鑑
①〜③の書類は国税庁のサイトからダウンロード可能ですが、税務署に足を運んで相談しながら確定申告する際は、現地で書類をもらうことも可能です。
もちろん④〜⑥も申告書に記入する際に必要になるので、事前にしっかり自分で整理しておきましょう。
※1:山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得及び一定の先物取引による雑所得等を指します。
参考サイト:国税庁「No.2240 申告分離課税制度」
step
2申告書などの作成・提出
step1で用意した書類や領収書などをもとに申告書の項目を埋めていきます。
分からないことがあれば最寄りの税務署に電話で確認することも可能です。ただし直前の時期は電話が混むので出来るだけ早く対応するようにしましょう。
申告書の提出は、次のstep3の「納税や還付の手続き」と一緒に行います。
step
3納税や還付の手続きをして確定申告完了
納税や還付の手続きをして確定申告完了になりますが、その際の手続きは、こちら3つのいずれかの方法で行うことができます。
- ① 税務署で確定申告する
- ② WEBで確定申告( e-Tax )する
- ③ スマホで確定申告する
①税務署で確定申告する
まず一つ目の方法は、最寄りの税務署に直接足を運んで手続きする方法です。
地域によっては商工会館などで行うケースもあります。
②WEBで確定申告( e-Tax )する
確定申告を何回も経験していて、特に相談する事なく進められる人は、e-Taxというシステムを使って自宅のパソコン上から手続きする事も可能です。
またマイナンバーカード方式とは別に、新たにID・パスワード方式も導入され、マイナンバーカードなしでも手続きが出来るようになりました。
こちらのIDとパスワードは運転免許証などの本人確認書類を税務署に持参すれば無料で即日発行してもらう事ができて、翌年以降も同じものが利用できるそうです。
参考サイト:国税庁「e-Tax利用の簡便化の概要について」
③スマホで確定申告する
2019年から、スマホでも確定申告が出来るようになり、PCの場合と同じく、IDとパスワードを使って手続きできます。
申告後の修正・申告漏れについて

確定申告した内容に、万が一誤りがあった場合でも後から修正する事が可能です。状況によって種類が異なり、大きく3つに分けられます。
1訂正申告について
訂正申告する場合は、最初に提出した確定申告書と同じフォーマットを使い、修正内容を反映させた確定申告書を再度提出します。
- 期限内に同じ人から2つ以上確定申告書が提出された場合は、最後に提出された申告書をその人の申告書として扱うルール
- 控除の証明書や領収書などはコピーしたものでよい
2更正の請求について
更正申告する場合は「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に、所得から差し引かれる金額や課税される所得などを記入して提出します。
更正の請求が行えるのは、5年以内までと決められているので注意する
3修正申告について
修正申告を行う場合は、下記の2つが必要になります。
- 「確定申告書B第一表」
- 「所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)」
修正申告の場合は延滞税や過少申告加算税が発生する仕組みになっているため、誤りに気が付いたら出来るだけ早く提出するように
それぞれの申告をする際の注意点や期限などについては、こちらのサイトにわかりやすくまとまっていますのでチェックしてみてください。
控除について

確定申告をするにあたって、控除にはどんな種類があるのか把握しておくことも大事なことです。
必要経費と同じように、節税につながるものなので、しっかりと目を通しておきましょう。
- 医療費控除(10万円以上、医療費の支払いがある場合に受けられる控除)
- 寄附金控除(ふるさと納税をした場合などに受けられる控除で、寄付した金額などによっても控除額は変わってくる)
- 雑損控除(災害、盗難、横領などによって損害を受けた場合に受けられる控除)
参考サイト:国税庁「所得から差し引かれる金額」(所得控除)
確定申告のまとめ
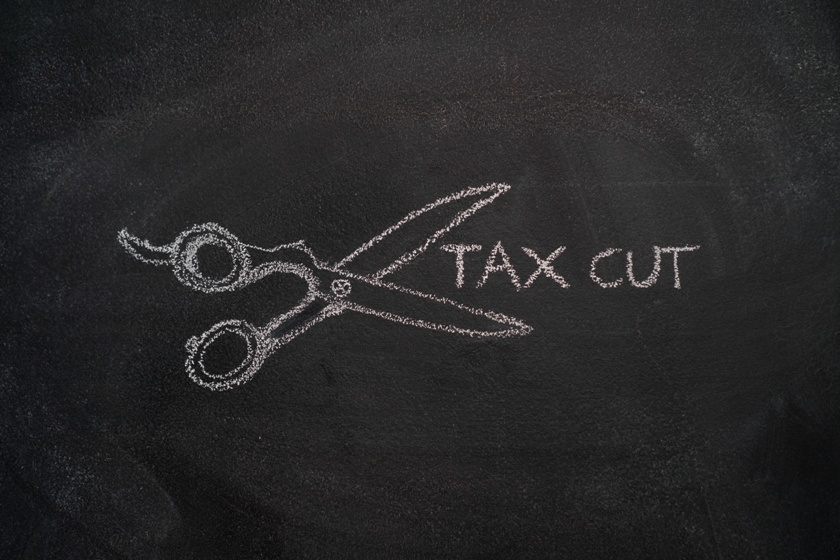
確定申告の種類や流れ、そして確定申告の注意点などを簡単に説明してきましたが、概要はつかめましたか?
納税は国民の義務であり支払うことは当然ですが、過払いの税金の還付があるかもしれませんし、節税につながることなので該当の方は期間内に確定申告をしましょう。
